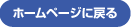 |
 |
館長講座![]() 平成11年度より実施
平成11年度より実施
ギャラリートーク![]() 平成11年度~平成18年度実施
平成11年度~平成18年度実施
| 実施年度 | 担当 | 各回のテーマ |
|---|---|---|
| 平成11年度 |
高野芳宏 | ①「多賀城の瓦」 ②「史生が語る律令時代の公務員生活」 |
| 須賀正美 | ①「下級役人のつぶやき」 | |
| 塩田達也 | ①「絵図から読み解く城下町と村」 | |
| 及川宏幸 | ①「ワラの神々」 | |
| 佐藤琴 | ①「酒呑童子物語図屏風と松島真景図巻」 | |
| 手塚均 | ①「縄文時代の植物食料」 | |
| 菅野恭彦 | ①「雑貨屋の風景」 | |
| 中村昌人 | ①「葬制・墓制 縄文人と現代人」 | |
| 関口重樹 | ①「仙台藩の商家建築 芭蕉の辻とその記憶」 | |
| 菊地逸夫 | ①「古墳時代のガラス玉」 | |
| 青木宏之 | ①「庶民と文人の旅 その1」 | |
| 吉澤幹夫 | ①「多賀城に配備された一兵士の話」 | |
| 小谷竜介 | ①「三陸の漁業」 | |
| 政次浩 | ①「中尊寺金色堂巻柱復元模造について 1」 | |
| 丹羽茂 | ①「現代に生きる古代の鍵 多賀城跡の発掘調査から」 | |
| 吉田博司 | ①「昭和40年代にタイムスリップ」 | |
| 伊藤博之 | ①「中世の山城」 | |
| 笠原信男 | ①「境の神ってどんな神」 | |
| 平成12年度 |
佐藤和彦 | ①「小田建万呂の人物像」②「木簡は便利だなぁ!!」 |
| 塩田達也 | ①「岩切周辺の中世的世界」②「文字の世界 古代・中世・近世」 | |
| 及川宏幸 | ①「ナマハゲの話」②「牡鹿半島の悪病送り」 | |
| 佐藤琴 | ①「東東洋筆「琴棋書画図屏風」について」 ②「東東洋筆「瀟湘八景図」について」 |
|
| 菅野恭彦 | ①「明治時代の貨幣」②「明治・大正期の雑誌について」 | |
| 須賀正美 | ①「防衛庁の新庁舎と多賀城」②「和同開珎の使い方」 | |
| 菊地逸夫 | ①「宮城県の中世陶器・窯」②「縄文土器の文様について」 | |
| 関口重樹 | ①「宮城県の洋風建築」②「宮城県の洋風建築2」 | |
| 中村昌人 | ①「間引き 生死の狭間で」②「藁人形と道祖神」 | |
| 青木宏之 | ①「庶民と文人の旅 その2」②「漆の実のみのるころ」 | |
| 吉澤幹夫 | ①「蕨手刀の謎」 | |
| 千葉正利 | ①「古代の鉄づくり」②「仙台藩の鉄銭鋳造について」 | |
| 政次浩 | ①「宮城の文化 近世禅僧の芸術」②「中尊寺経について」 | |
| 笠原信男 | ①「近世の瓦屋根」②「仙台藩のおかかえ職人」 | |
| 小谷竜介 | ①「フカヒレ・アワビ 宮城の名産品」②「型紙を作るわざ」 | |
| 穂積達郎 | ①「化石人類の謎をさぐる」②「懸仏について(名取熊野那智神社)」 | |
| 及川規 | ①「文化財の保存と展示1 保存の環境」 | |
| 手塚均 | ①「遺構の保存処理 はぎ取り資料の活用」 ②「縄文時代の第二の道具 土製仮面を中心に」 |
|
| 高野芳宏 | ①「発掘された古代の文書」 | |
| 小井川和夫 | ①「仙台祭」②「仙台祭」 | |
| 桑原滋郎 | ①「多賀城廃寺跡、附寺院と多賀城」②「漆紙文書について」 ③「仙台城跡の櫓復原」 |
|
| 平成13年度 |
手塚均 | ①「お墓アラカルト」②「やきものと窯」 |
| 塩田達也 | ①「中尊寺 その中世的様相」②「音と人の風景」 | |
| 及川宏幸 | ①「ビデオで見る民俗行事 岩手県二戸市福田の人形まつり」 ②「教会堂の建てられる背景 宮城のハリストス正教伝道史」 |
|
| 佐藤琴 | ①「絵画探検1」②「絵画探検2」 | |
| 穂積達郎 | ①「中世の写本と写経 ヨーロッパと日本の技術と装飾」 ②「日本の鎧について ヨーロッパの甲冑について」 |
|
| 中村昌人 | ①「輝いていた瞬間 昭和30・40年代を考える」 ②「旅に関するエトセトラ」 |
|
| 須賀正美 | ①「縄文人が着ていた服」②「陸奥の国司のプロフィール」 | |
| 青木宏之 | ①「東京オリンピックのころ」②「“養賢堂”と齊藤竹堂」 | |
| 菊地逸夫 | ①「骨角器のはなし」②「おおむかしの玉」 | |
| 関口重樹 | ①「県内に遺る戦前の教会建築 石巻ハリストス正教会を中心に」 ②「宮城集治監」 |
|
| 山田晃弘 | ①「宮城県の前・中期旧石器時代」②「後期旧石器時代の暮らし」 | |
| 及川規 | ①「出土遺物を“じょうぶ”にする方法」 ②「見えない(!?)ものを見る 博物館における科学の眼」 |
|
| 高野芳宏 | ①「人面墨書土器について」②「古代の土木技術」 | |
| 小谷竜介 | ①「型紙売る人々」②「アワビあれこれ」 | |
| 桑原滋郎 | ①「貝塚の発掘調査」②「多賀城碑について」 | |
| 政次浩 | ①「中尊寺宋版一切経について」②「中尊寺経を護る」 | |
| 丹羽茂 | ①「土偶と埴輪 その1」②「埴輪について その2」 | |
| 籠橋俊光 | ①「仙台藩の大肝入り」②「内済について」 | |
| 小井川和夫 | ①「縄文土器の編年1」②「縄文土器の編年2」 | |
| 笠原信男 | ①「神の意志を知る方法 ト占」②「けがれをきよめる はらい」 | |
| 千葉正利 | ①「銅鏡、その不思議な輝き」②「金属のはなし」 | |
| 佐藤和彦 | ①「多賀城碑の碑堂」②「“エミシ”と呼ばれた人々」 | |
| 平成14年度 |
手塚均 | ①「縄文・弥生時代の木製品について」 ②「晩期の土偶について 遮光器土偶を中心に」 |
| 塩田達也 | ①「大伴家持と多賀城 主に赴任・遙任の論点について」 ②「墨書土器の世界」 |
|
| 及川宏幸 | ①「箕の話」②「鍬の話」 | |
| 佐藤琴 | ①「絵画探検4 牡丹と猫」②「絵画探検5」 | |
| 千葉正利 | ①「どんぐりを食べる」②「仙台藩の洋式高炉」 | |
| 中村昌人 | ①「江戸の遊び 花見と虫撰」②「江戸時代の危機管理」 | |
| 籠橋俊光 | ①「往来物に見る仙台」②「肝入の仕事 今野家文書を読む」 | |
| 菊地逸夫 | ①「馬に関するエトセトラ」②「ちょっと気になる“複製品”」 | |
| 須賀正美 | ①「明治20年上野~塩釜間鉄道開業」②「多賀城の兵士たち」 | |
| 関口重樹 | ①「仙台藩の商家建築 芭蕉の辻とその記憶」②「宮城県の電気物語」 | |
| 生田和宏 | ①「古代の文房具 硯の系譜を中心として」 ②「古代の文房具Ⅱ 墨の系譜を中心として」 |
|
| 高野芳宏 | ①「明治・大正期の多賀城跡」②「万灯会について」 | |
| 後藤彰信 | ①「宮城の思想家 1鈴木文治 友愛会結成まで」 ②「宮城の思想家 2吉野作造 関東大震災と吉野」 |
|
| 政次浩 | ①「金光明王最勝王経金字宝塔曼荼羅図について」②「鏡像と御正躰」 | |
| 山田晃弘 | ①「石器は古墳時代にも使われていた」 ②「石器作りに使われた石材 どんな石が適していたか」 |
|
| 小谷竜介 | ①「絵馬の話」②「エビス様って」 | |
| 木村健一 | ①「和同開珎はどんなお金?」②「お金の歴史について」 | |
| 佐藤和彦 | ①「古代陸奥国の鉱物資源」②「大伴家持と陸奥国」 | |
| 丹羽茂 | ①「埴輪について その3 靫形埴輪について」②「埴輪について その4」 | |
| 及川規 | ①「遺物の年代を知る方法 いろいろな年代測定法について」 ②「歴史資料と科学分析Ⅰ 分析の原理とともに」 |
|
| 笠原信男 | ①「中世の祭礼 奥州探題大崎氏を例として」②「石臼 挽臼と粉食」 | |
| 小井川和夫 | ①「骨角器の製作とその素材」②「アイヌの刀」 | |
| 進藤秋輝 | ①「小塔供養について」②「百萬塔について」 | |
| 平成15年度 |
後藤彰信 | ①「宮城の思想家たち 3千葉卓三郎」 ②「宮城の思想家たち 4新井奥邃」 |
| 生田和宏 | ①「古代の文房具Ⅲ」 ②「文物からみた日中交流 中国鉛釉陶の系譜」 |
|
| 佐藤琴 | ①「絵画探検6 東東洋筆「耕織図」について」 ②「絵画探検7 菅井梅関筆「月下漁夫図」について」 |
|
| 小谷竜介 | ①「干し鮭・塩引き・荒巻」②「漁具+博覧会=?」 | |
| 千葉正利 | ①「金を採ってみませんか」②「平泉の金はどこから来たのか?」 | |
| 手塚均 | ①「岩偶について」②「竪穴住居について」 | |
| 須賀正美 | ①「陸奥国の変遷」②「三十八年戦争後の陸奥国」 | |
| 小井川和夫 | ①「中世陶器」②「中世陶器Ⅱ」 | |
| 及川宏幸 | ①「野鍛冶の話」②「漁村の年中行事」 | |
| 塩田達也 | ①「戦争の“正義”とは何か」 ②「多賀城周辺ぶらり旅 墨書土器を中心に」 |
|
| 菊地逸夫 | ①「貝塚伝説のはなし」 ②「縄文時代の植物食 ドングリとトチの実を中心に」 |
|
| 及川規 | ①「歴史資料と科学分析Ⅱ」②「歴史資料と科学分析Ⅲ」 | |
| 政次浩 | ①「紺紙金銀字交書一切経の書写事業について」 ②「紺紙金字交書一切経の書写事業について」 |
|
| 山田晃弘 | ①「里浜人の漁撈生活」②「縄文時代の水場遺構について」 | |
| 笠原信男 | ①「臼と杵」②「花巻土人形」 | |
| 籠橋俊光 | ①「仙台藩絵図考」②「涌谷」 | |
| 丹羽茂 | ①「埴輪について その5」 ②「埴輪について その6 盾を持つ人について考える」 |
|
| 関口重樹 | ①「宮城集治監と雄勝石」②「看板建築」 | |
| 佐藤和彦 | ①「多賀城で働く人々」②「往にし方びとのカレンダー」 | |
| 高野芳宏 | ①「多賀城瓦の窯跡」②「下級役人の執務風景」 | |
| 中村昌人 | ①「合併と分割 中央集権と地方分権」伊達家文書 ②「合併と分割Ⅱ 国と企業と庶民の生きる道」 |
|
| 木村健一 | ①「古代の刑罰について」②「古代の税について」 | |
| 進藤秋輝 | ①「国府の成立過程と多賀城1」②「国府の成立過程と多賀城2」 | |
| 平成16年度 |
後藤彰信 | ①「宮城の思想家たち 5二階堂嘉平」 ②「宮城の思想家たち 6沢来太郎」 |
| 笠原信男 | ①「カゴとザル」②「漆と漆器」 | |
| 政次浩 | ①「中尊寺所蔵宋版経について2」②「金色堂の装飾」 | |
| 須賀正美 | ①「陸奥国の東山道」②「駅使が走る!東山道」 | |
| 及川規 | ①「出土遺物の保存処理」②「文化財の保存について」 | |
| 木村健一 | ①「律令国家のしくみについて」②「富本銭から和同開珎へ」 | |
| 小谷竜介 | ①「農具と改良」②「河童の川流れ」 | |
| 生田和宏 | ①「文物からみた日中交流Ⅱ」②「文物からみた日中交流Ⅲ」 | |
| 佐藤琴 | ①「絵画探検8 山水図」②「絵画探検9 福禄寿」 | |
| 籠橋俊光 | ①「慶応四年の仙台藩」②「足軽について」 | |
| 加藤道男 | ①「貝塚と製塩」②「貝塚と製塩土器」 | |
| 中村昌人 | ①「合併と分割Ⅲ」②「見立番付」 | |
| 佐藤和彦 | ①「古代の陸奥国と出羽国」②「伊治公呰麻呂反く」 | |
| 丹羽茂 | ①「埴輪について その7」 ②「埴輪について その8 鳥について考える」 |
|
| 塩田達也 | ①「宮城に残る白河文書」②「展示室の動物たち」 | |
| 関口重樹 | ①「宮城県の教会建築 ハリストス正教」 ②「宮城県の教会建築 カトリックとプロテスタント」 |
|
| 阿部博志 | ①「土偶とは 1」②「ナラ林の復元住居」 | |
| 手塚均 | ①「奥州藤原氏とやきもの」②「古墳時代と土器」 | |
| 及川宏幸 | ①「小正月のツクリモノ アワボヒエボ」②「小正月のツクリモノ」 | |
| 千葉正利 | ①「古代東北の製鉄事業」②「古代の鍛冶工房」 | |
| 高野芳宏 | ①「払田柵の発見」②「多賀城の材木塀」 | |
| 山田晃弘 | ①「縄文時代の木製容器」②「縄文時代の弓と矢」 | |
| 平成17年度 |
山田晃弘 | ①「縄文時代の編物 ザル・カゴ類について」 ②「弥生文化のはじまり」 |
| 阿部博志 | ①「縄文時代の動物型土製品について」②「縄文時代の土製仮面」 | |
| 塩田達也 | ①「古代の文字と人々 墨書土器を中心に」 ②「宮城に残る白河文書 結城白河家とその文書の伝来」 |
|
| 千葉正利 | ①「宮城にあった金山」②「海を渡る」 | |
| 丹羽茂 | ①「埴輪について その9 翳(さしば)について考える」 ②「埴輪について その10 盾について考える」 |
|
| 手塚均 | ①「宮城県を中心とした古墳時代前期(4世紀)の墳墓と集落」 ②「食と器」 |
|
| 水沼節郎 | ①「宮城が生んだジャーナリスト 岩淵辰雄」 ②「宮城が生んだジャーナリスト 岩淵辰雄 その2」 |
|
| 及川規 | ①「文化財にやさしい環境」 ②「文化財にやさしい環境 “木”は文化財にやさしいか?Ⅱ」 |
|
| 政次浩 | ①「金色堂の装飾2」②「名取市熊野那智神社の懸仏について」 | |
| 小谷竜介 | ①「型紙を作る」②「柄鏡について」 | |
| 須賀正美 | ①「古代陸奥国の交通」②「古代東北の水上交通」 | |
| 鈴木陽子 | ①「川とともに生きる「北上川の水運」その1」 ②「川とともに生きる「北上川の水運」その1」 |
|
| 後藤彰信 | ①「宮城の新聞 1総説」②「宮城の新聞 2総説 続」 | |
| 籠橋俊光 | ①「町と村のあいだ 近世仙台近郊のひとびと」 ②「伊達宗重の書状」 |
|
| 関口重樹 | ①「仙台城下の牢獄」②「雑貨屋の復元」 | |
| 佐藤琴 | ①「絵画探検10 「東東洋 日本三景を旅した画家」」 ②「絵画探検11 「亀」」 |
|
| 高野芳宏 | ①「漆紙文書 「九九八十一」」②「元の姿にせまる(小話)」 | |
| 渡邊直樹 | ①「古墳社会の成立 その1 水田稲作農耕技術の受容」 ②「古墳社会の成立 その2 東北地方の水田稲作農耕文化の特性」 |
|
| 白鳥良一 | ①「縄文時代の釣」②「縄文時代のモリとヤス」 | |
| 高橋栄一 | ①「前方後円墳の時代1 古墳時代中期の宮城県」 ②「前方後円墳の時代2 古墳時代中期の集落」 |
|
| 及川宏幸 | ①「暦の話」②「民具を見る 収蔵資料から生活と時代を探る」 | |
| 平成18年度 |
小谷竜介 | ①「宮城の大網漁」②「切り紙と修験者」 |
| 塩田達也 | ①「牛玉宝印と起請文」②「中世・近世のペットたち」 | |
| 高橋栄一 | ①「古墳時代後期の墳墓について」②「宮城の横穴について」 | |
| 籠橋俊光 | ①「変わった古文書たち」②「村絵図の世界」 | |
| 水沼節郎 | ①「ラジオと大衆」②「マスメディアと生活」 | |
| 鈴木陽子 | ①「カマ神様の話 1」②「カマ神様の話 2」 | |
| 政次浩 | ①「名取熊野三山」②「慈覚大師円仁と平泉」 | |
| 関口重樹 | ①「芭蕉の辻」②「屋根 空間を覆うもの」 | |
| 山田晃弘 | ①「縄文時代の四季の食べ物」②「米作りの道具」 | |
| 及川規 | ①「文化財の保存と修復 最近の話題から」 ②「文化財の保存と修復 最近の話題からⅡ」 |
|
| 及川宏幸 | ①「民具を見る 2」②「民具を見る 3明かりと暖房」 | |
| 渡邊直樹 | ①「川村瑞賢と阿武隈川舟運」 ②「古墳社会の成立 その3 穴をあけた土器のはなし」 |
|
| 須賀正美 | ①「古代多賀城役人の食事風景」②「吉田初三郎の鳥瞰図」 | |
| 手塚均 | ①「田柄貝塚について」②「縄文人のおしゃれ 櫛」 | |
| 千葉正利 | ①「海を渡る 2」②「宮城にあった鉱山」 | |
| 高野芳宏 | ①「多賀城南の町並み発見に至るまで」②「瓦・硯についた顔料」 | |
| 後藤彰信 | ①「宮城の新聞 3総説 続続」②「宮城の新聞 4総説 続続続」 | |
| 丹羽茂 | ①「杉山コレクションの埴輪 総論」②「縄文土器の歴史 その1」 | |
| 佐藤琴 | ①「絵画探検12 東東洋」②「絵画探検13 富士」 | |
| 白鳥良一 | ①「縄文土器の分布と変遷」②「古代エミシのくらし」 | |
| 阿部博志 | ①「縄文前・中期の土偶」②「縄文時代のアスファルト利用」 | |
![]()
展示解説![]() 平成19年度~平成20年度実施
平成19年度~平成20年度実施
| 実施年度 | 担当 | 各回のテーマ |
|---|---|---|
| 平成19年度 |
高野芳宏 | ①古代 ②古代詳細 |
| 水沼節郎 | ①近現代 ②近現代 | |
| 須賀正美 | ①古代 ②古代 | |
| 鈴木陽子 | ①近世詳細 ②近世詳細 | |
| 塩田達也 | ①テーマ3 ②テーマ3 | |
| 阿部博志 | ①縄文 ②縄文詳細 | |
| 手塚均 | ①縄文 ②縄文 | |
| 千葉正利 | ①テーマ3 ②テーマ3 | |
| 齋藤賢之 | ①近世 ②近世 | |
| 市村賢則 | ①縄文 ②縄文 | |
| 政次浩 | ①古代~中世 ②中世 | |
| 小谷竜介 | ①近世 ②近世 | |
| 平成20年度 |
水沼節郎 | ①近現代~雑貨屋について ②近現代~続・雑貨屋について |
| 須賀正美 | ①古代~国府多賀城の時代 | |
| 政次浩 | ①古代から中世へ~中尊寺経について ②中世~新宮寺一切経について |
|
| 阿部博志 | ①弥生~古代 ②弥生時代について | |
| 籠橋俊光 | ①武士の様子 | |
| 市村賢則 | ①縄文~縄文人のくらし ②縄文人の生活 | |
| 塩田達也 | ①テーマ展示Ⅲ~宮城に残る白河文書 ②古代・中世 祈りの世界 | |
| 手塚均 | ①弥生・古墳・古代~北東北社会の交流 ②里浜貝塚について | |
| 及川規 | ①近現代~電気の時代 ②資料を展示するために~出土遺物の保存処理 |
|
| 阿部恵 | ①貝塚について ②貝塚の世界 | |
| 鈴木陽子 | ①中世・近世・近現代~絵馬を読む ②近世詳細~ワラの神々 | |
| 佐久間光平 | ①旧石器~二万年前の狩人の道具 ②二万年前のキャンプ跡 | |
![]()
体験教室 平成11年度より実施
| 実施年度 | 教室名(実施回数:所要日数) <特記事項がない場合、(1回:1日)の実施> |
|---|---|
| 平成11年度 | 年間テーマ・・・「つくる」・「行なう」 縄文土器作り教室(1回:2日間)・紙漉き教室・凧作り教室・編み布作り教室(2回:2日間) |
| 平成12年度 | 年間テーマ・・・「つくる」 編み布を作ろう(2回:2日間)・七夕を作ろう・紙を作ろう・勾玉を作ろう(2回:1日)・ドキ土器体験(1回:3日間)・切り紙を作ろう・凧を作ろう・ひな人形を作ろう・とんぼ玉を作ろう |
| 平成13年度 |
年間テーマ・・・「むかしの技術」・「年中行事に親しもう」 編み布作り・縄文時代のペンダント作り・七夕飾りを作ろう・盆棚を飾ろう・十五夜飾りを作ろう・縄文土器作り・古代食(どんぐり)を食べよう・お正月の切り紙作り・お正月遊びに親しもう・凧作り・ひな人形を作ろう・石器作り 体験イベント「博物館まつり はくぶつかんへいこう」10月7日実施 <体験をとおして歴史を体感> 「誰が一番、昔の人:火おこし」・「誰が一番、昔の人:縄のはや作り」・「誰が一番、昔の人:石で切る」・「歴史を感じて作ってみよう:勾玉」・「歴史を感じて作ってみよう:伝統のおもちゃ」・「民話を聞こう」・「伝統遊びに挑戦」・「街頭紙芝居がやってきた」 その他、<展示などを通してより身近に歴史を感じてもらう企画>や<国府多賀城駅開業にちなんだ企画>を実施 |
| 平成14年度 |
年間テーマ1・・・「くらしのわざ」 ワラゾウリをつくろう・七夕馬をつくろう・月見団子をつくろう・しめ飾りをつくろう・マユダマ 年間テーマ2・・・「大昔の技術」 縄文土器をつくる・古代食体験・装身具・石器つくり 夏休み体験教室 七夕飾り・銅鏡作り 体験イベント「秋の見覚 まるかじり博物館」(開館記念行事)10月6日実施 <体験を通して歴史を体感> 「昔の遊びを体験しよう」・「昔の技に挑戦:縄の早つくり」・「昔の技に挑戦:火おこし」・「昔の技に挑戦:弓矢」・「昔の技に挑戦:独楽廻し大会」・「歴史を感じて作ってみよう:作ってみよう!勾玉」・「歴史を感じて作ってみよう:出張こども歴史館・色いろ」 その他、パネル展示・上映会・ギャラリートーク・館内オリエンテーリング・独楽作り実演・史跡巡り「多賀城政庁跡コース・多賀城廃寺跡コース」を実施 |
| 平成15年度 |
年間テーマ1・・・「くらしのわざ」 ワラゾウリをつくろう・七夕馬をつくろう・月見団子をつくろう・しめ飾りをつくろう・マユダマ 年間テーマ2・・・「大昔の技術」 骨角器(釣り針作り)・縄文土器作り(1回:2日間 成形と焼成)・古代食体験(ドングリ)・装身具(トンボ玉)・石器 体験イベント「秋の見覚 まるかじり博物館」(開館記念行事)10月12日実施 <体験を通して歴史を体感> 「昔の遊びを体験しよう」・「昔の技に挑戦:縄の早つくり」・「昔の技に挑戦:火おこし」・「昔の技に挑戦:弓矢」・「昔の技に挑戦:砂金採り」・「歴史を感じて作ってみよう:作ってみよう!勾玉」・「歴史を感じて作ってみよう:作ってみよう!トンボ玉」・「特別企画:紙芝居」 その他、パネル展示・史跡巡り「多賀城政庁跡コース・多賀城廃寺跡コース」を実施 |
| 平成16年度 |
年間テーマ1・・・「くらしのわざ」 ワラゾウリをつくろう・七夕馬をつくろう・月見団子をつくろう・しめ飾りをつくろう・マユダマ 年間テーマ2・・・「大昔の技術」 骨角器(釣り針作り)・古代の陶芸技術を学ぶ(1回:3日間 成形 施釉 窯出)・古代食体験(ドングリ)・装身具(トンボ玉) 体験イベント「秋の見覚 まるかじり博物館」(開館記念行事)10月9日実施 ・・・台風の直撃を受け大幅に規模を縮小して開催 |
| 平成17年度 |
年間テーマ1・・・「くらしのわざ」 ワラゾウリをつくろう・七夕馬をつくろう・月見団子をつくろう・しめ飾りをつくろう・マユダマ 年間テーマ2・・・「大昔の技術」 古代の陶芸技術を学ぶ(1回:3日間 成形 施釉 窯出)・古代食体験(ドングリ)・装身具(トンボ玉) 体験イベント「秋の見覚 まるかじりはくぶつかん」10月8日実施 <体験を通して歴史を体感> 「縄文体験ツアー(丸木舟体験・火おこし・石器作り・土器で調理実習・弓矢体験)」 「粉ひき体験ツアー(籾すり・粉ひき・調理実習)」 「バックヤード・ツアー」 「昔の遊びを体験しよう」・「昔の技に挑戦:火おこし」・「昔の技に挑戦:弓矢」・「昔の技に挑戦:砂金採り」・「歴史を感じよう:勾玉作り」・「歴史を感じよう:昔の食べ物」 その他、パネル展示・史跡巡り「多賀城政庁跡コース・多賀城廃寺跡コース」を実施 |
| 平成18年度 |
縄文土器を作ろう(1回:2日間)・トンボ玉を作ろう 春の体験イベント「春のわくわく体験見本市」:5月13日実施 秋の体験イベント「秋の見覚 まるかじりはくぶつかん」:10月7日実施 |
| 平成19年度 |
夏の体験教室 縄文土器を作ろう・丸木舟をこいでみよう・縄文の布を編んでみよう・弓矢で獲物をねらおう・ 銅鏡を作ろう・勾玉を作ろう・縄文の櫛(くし)を作ろう・ガラスの玉をつくろう 冬の体験教室 ドングリを食べてみよう・トンボ玉をつくろう・「小うちぎ」を着てみよう・昔遊びを楽しもう・ 切り紙を作ろう・和菓子を作ろう・ワラゾウリを作ろう・石うすをひいてみよう 春の体験イベント「春のわくわく体験見本市」:5月12日実施 秋の体験イベント「秋の見覚 まるかじりはくぶつかん」:10月6日実施 |
| 平成20年度 |
夏の体験教室 縄文土器をつくろう・丸木船をこいでみよう・縄文ポシェットをつくろう・勾玉をつくろう・ ぎっちょうで遊ぼう・石包丁をつくろう・縄文の布を編んでみよう・弓矢で獲物をねらおう・ 「小うちぎ」を着てみよう・銅鏡をつくろう 冬の体験教室 ワラゾウリをつくろう・ドングリを食べてみよう・切り紙をつくろう・和菓子をつくろう・ トンボ玉をつくろう・石臼をひいてみよう・ガラスの玉をつくろう・絵の具をつくろう 春の体験イベント「春のわくわく体験見本市」:5月10日実施 秋の体験イベント「秋の見覚 まるかじりはくぶつかん」:10月11日実施 |
| 平成21年度 |
夏の体験教室 縄文土器をつくろう・丸木舟をこいでみよう・絵の具をつくろう・ぎっちょうで遊ぼう・ ガラス玉をつくろう・石臼をひいてみよう・「こうちぎ」を着てみよう・弓矢で獲物をねらおう・ 石包丁をつくろう・砂金で一攫千金 冬の体験教室 トンボ玉をつくろう・ドングリを食べてみよう・切り紙をつくろう・和菓子をつくろう・ 縄文ポシェットをつくろう・縄文の布を編んでみよう・ワラゾウリをつくろう・勾玉をつくろう 春の体験イベント「春のわくわく体験見本市」:5月9日実施 秋の体験イベント「秋の見覚 まるかじりはくぶつかん」:10月10日実施 |
| 平成22年度 |
夏の体験教室 縄文土器をつくろう・丸木舟をこいでみよう・ガラス玉をつくろう・石臼をひいてみよう・ 七夕馬をつくろう・砂金で一攫千金・縄文の布を編んでみよう・弓矢で獲物をねらおう・ 絵の具をつくろう・ぎっちょうで遊ぼう 冬の体験教室 和菓子をつくろう・空き缶カンテラをつくろう・トンボ玉をつくろう・切り紙をつくろう・ 昔の衣装を着てみよう・勾玉をつくろう 春の体験イベント「春のわくわく体験見本市」:5月8日実施 秋の体験イベント「秋の見覚 まるかじりはくぶつかん」:10月9日実施 冬の体験イベント「冬も元気にはくぶつかん!」:2月5日実施 |
![]()
古文書講座入門編 平成14年度から実施
平成11年度から実施してきた「古文書講座」は、平成14年度より「入門編」と「中級編<中世文書コース>・
<近世文書コース>」に編成して実施。
| 実施年度 | 担当 | 概 要 |
|---|---|---|
| 平成14年度 | 塩田達也 | 全3回 ①「古文書への扉」②「辞書に親しむ」③「様式や慣用句を知る」 |
| 平成15年度 | 塩田達也 | 全4回 ①「古文書への扉」 ②「仮名文字の世界」 ③「漢文体に親しむ 中世・近世の武家文書」 ④「漢字仮名交じり文を読む」 |
| 平成16年度 | 塩田達也 | 全4回 ①「古文書への扉」 ②「仮名文字の世界」 ③「漢文体に親しむ 中世・近世の武家文書」 ④「漢字仮名交じり文を読む」 |
| 平成17年度 | 塩田達也 | 全3回 ①「古文書への扉」②「辞書に親しむ」③「様式や慣用句を知る」 |
| 平成18年度 | 塩田達也 | 全3回 ①「古文書への扉」②「辞書に親しむ」③「様式や慣用句を知る」 |
| 平成19年度 | 塩田達也 | 全3回 ①「古文書への扉」②「辞書に親しむ」③「様式や慣用句を知る」 |
| 平成20年度 | 塩田達也 | 全3回 ①「古文書への扉」②「辞書に親しむ」③「様式や慣用句を知る」 |
| 平成21年度 | 塩田達也 | 全3回 ①「古文書への扉」②「辞書に親しむ」③「様式や慣用句を知る」 |
![]()
古文書講座中級編 平成14年度から実施
平成11年度から実施してきた「古文書講座」は、平成14年度より「入門編」と「中級編<中世文書コース>・
<近世文書コース>」に編成して実施。
| 実施年度 | 担当 | 概 要 |
|---|---|---|
| 平成14年度 | 中世:塩田達也 | 全4回:中世文書を読む 書状を中心に |
| 近世:籠橋俊光 | 全3回:「天明凶歳録」を読む | |
| 平成15年度 | 中世:塩田達也 | 全4回:中世文書を読む 書状を中心に |
| 近世:籠橋俊光 | 全4回:近世の地方文書を読む 今野家文書「御式目」を読む | |
| 平成16年度 | 中世:塩田達也 | 全4回:中世文書を読む 書状を中心に |
| 近世:籠橋俊光 | 全4回:戊辰戦争の記録を読む 涌谷伊達家文書「秋田口軍事御用留」を読む |
|
| 平成17年度 | 中世:塩田達也 | 全4回:中世文書を読む 書状を中心に |
| 近世:籠橋俊光 | 全4回:境界論争文書を読む 涌谷伊達家文書「中埣谷地練宇川谷地巻」を読む |
|
| 平成18年度 | 中世:塩田達也 | 全4回:中世文書を読む 書状を中心に |
| 近世:籠橋俊光 | 全4回:旅関係文書を読む | |
| 平成19年度 | 中世:塩田達也 | 全4回:中世文書を読む 書状を中心に |
| 近世:籠橋俊光 | 全4回:涌谷伊達家・谷地出入関係文書を読む | |
| 平成20年度 | 中世:塩田達也 | 全4回 |
| 近世:籠橋俊光 | ||
| 平成21年度 | 中世:塩田達也 | 全4回 |
| 近世:籠橋俊光 | ||
| 平成22年度 | 中世:塩田達也 | 全4回 |
| 近世:籠橋俊光 | ||
![]()
史料講読講座 平成12年度より実施
| 実施年度 | 担当・概要 |
|---|---|
| 平成12年度 | 桃生城関係の資料を読みながら、多賀城の出先機関として置かれた桃生城の歴史について調べ、発表しあうという内容。 |
| 平成13年度 | 全6回 「古代から近現代までの宮城県関係の史料」 ①須賀正美「史料から見る古代多賀城1」 ②須賀正美「史料から見る古代多賀城2」 ③塩田達也「中世多賀国府を探る1」 ④塩田達也「中世多賀国府を探る2」 ⑤青木宏之「齋藤竹堂“鴉片始末”を読む」 ⑥籠橋俊光「幕末維新の記録を読む」 |
| 平成14年度 | 全4回 「史料に見る鉱物資源」 ①佐藤和彦「陸奥国天平産金の史料を読む」 ②塩田達也「都へのぼる奥州の金 古代から中世にかけての政治・収取体制の中で」 ③千葉正利「仙台藩の炯屋製鉄」 ④後藤彰信「鉱山の近代化と鉱山労働者の生活」 |
| 平成15年度 | 全4回 「日本の法と社会」 ①-1木村健一「十七条憲法から当時の社会を考える」 ①-2須賀正美「律令からみる古代東北社会」 ② 塩田達也「鎌倉幕府法の特質 御成敗式目の成立を中心に」 ③ 籠橋俊光「仙台藩「百姓条目」を読む」 ④ 後藤彰信「自由民権運動と国民の創出 私擬憲法にみる」 |
| 平成16年度 | 全4回 「平和と戦争」 ①佐藤和彦「東北における三十八年戦争と戦後の情勢」 ②塩田達也「第二回豊臣平和令を読む 自力救済から法による紛争解決へ」 ③籠橋俊光「仙台藩の軍役と蝦夷地反乱」 ④後藤彰信「近代日本の平和と戦争 日露戦争100周年をめぐって」 |
| 平成17年度 | 全4回 「古代の道」 須賀正美「古代の道①~④」 |
| 平成18年度 | 全4回 「天災は忘れたころにやってくる」 ①籠橋俊光「災害記録論 序説 仙台藩を事例に」 ②塩田達也「中世の災害・飢饉と国家 鎌倉期を中心として」 ③須賀正美「古代の災害 地震記録を中心として」 ④後藤彰信「三陸大海嘯の映像と記録」 |
| 平成19年度 | 全4回 「古代出羽の争乱」(須賀正美) ①「元慶の乱『日本三大実録』から 1」 ②「元慶の乱『日本三大実録』から 2」 ③「後三年の役『奥州後三年記』から 1」 ④「後三年の役『奥州後三年記』から 1」 |
| 平成20年度 | 全4回 「古代陸奥の争乱」(須賀正美) ①「三十八年戦争 1」 ②「三十八年戦争 2」 ③「前九年の役 1」 ④「前九年の役 2」 |
| 平成21年度 | 全4回 「伊達騒動-涌谷伊達家文書からの検討-」(籠橋俊光) ①「序説」 ②「宗重と宗勝」 ③「涌谷家中の伊達騒動」 ④「伝承される伊達騒動」 |
| 平成22年度 | 全4回 「文献資料から見た多賀城」(須賀正美) ①「多賀城の創建まで」 ②「多賀城政庁第Ⅰ期~第Ⅱ期の造営」 ③「多賀城政庁第Ⅱ期の時代」 ④「多賀城政庁第Ⅲ期の時代」 |
![]()
ビデオライブラリー講座 平成14年度~平成20年度実施
| 実施年度 | 担当・概要 |
|---|---|
| 平成14年度 | 全3回 「今に生きる職人の技」 ①笠原信男「木地師のわざ 椀とこけし」 ②笠原信男「桶のふしぎ」 ③及川宏幸「竹細工 籠や笊の製作工程を見る」 |
| 平成15年度 | 全4回 「民俗芸能 宮城の神楽」 ①笠原信男「仙台市通町熊野神社神楽」 ②笠原信男「異伝の法印神楽 薬莱山三輪流神楽」 ③笠原信男「浜の法印神楽」 ④笠原信男「十二座神楽・名取市神楽」 |
| 平成16年度 | 全4回 「民俗芸能 宮城県の鹿踊」 ①及川宏幸「概略編」 ②及川宏幸「仙台鹿踊」 ③及川宏幸「仙台藩領北部の鹿踊り」 ④及川宏幸「注目すべき人と鹿踊組」 |
| 平成17年度 | 全3回 「民俗芸能 東北の神楽」 ①小谷竜介「早池峰神楽と黒森神楽(岩手県)」 ②小谷竜介「能舞(青森県下北半島)」 ③小谷竜介「霜月神楽(秋田県横手市<旧大森町>)」 |
| 平成18年度 | 全4回 「田楽・舞楽・延年 神楽以前の芸能」 ①小谷竜介「庄内地方の田楽 大物忌神社花笠舞と高寺八講」 ②小谷竜介「金砂大祭礼(茨城県常陸太田市)」 ③小谷竜介「林家舞楽(山形県河北町)」 ④小谷竜介「太平楽 地方舞楽の比較」 |
| 平成19年度 | 全4回 「東北地方の鹿踊」 ①小谷竜介「岩手県にみられる鹿踊 奥州市周辺の鹿踊を中心に」 ②小谷竜介「福島県にみられる三匹獅子舞」 ③小谷竜介「秋田県のササラ」 ④小谷竜介「山形県の三匹獅子舞」 |
| 平成20年度 | 全4回 「旧仙台領の神楽」 ①小谷竜介「浜の法印神楽-雄勝法印神楽を中心として」 ②小谷竜介「流法印神楽-浅部法印神楽を中心として」 ③小谷竜介「大乗神楽-和賀大乗神楽を中心として」 ④小谷竜介「三輪流法印神楽-薬莱神社三輪流神楽を中心として」 |
![]()
民俗芸能講座 平成21年度より実施
| 実施年度 | 担当・概要 |
|---|---|
| 平成21年度 | 全4回 ①笠原信男「お客さんを楽しませる-南部神楽」 ②笠原信男「滑稽な仕草と舞-獅子舞と七福神舞」 ③笠原信男「おごそかな獅子-獅子神楽」 ④笠原信男「豊穣への願い-田植踊」 |
| 平成22年度 | 全4回 ①笠原信男「田植踊①」 ②笠原信男「田植踊②」 ③笠原信男「獅子踊・剣舞①」 ④笠原信男「獅子踊・剣舞②」 |
開放講座 平成12年度~平成18年度実施
本講座は平成12年度より、宮城県教育庁生涯学習課の「県民大学開放講座」の一環として開催。
平成16年度から平成18年度までは当博物館の独自事業として実施。
注:下記の表中において、担当者について、敬称を省略させていただいております。
また、所属等については実施年度段階のものを掲載させていただいております。
氏名の後に所属等の記載が無いものについては当博物館所属です。
ご了承願います。
オープン講座 平成19年度より実施