 |
 |
 |
 |
 |
|
赤漆塗り壷形土器
(縄文晩期)
青森県八戸市
是川中居遺跡
国重要文化財
八戸市縄文学習館蔵 |
赤く塗られた
遮光器土偶
(縄文晩期)
岩手県久慈市
大芦Ⅰ遺跡
岩手県教育委員会蔵 |
鹿角製腰飾り
(縄文晩期)
宮城県東松島市
里浜貝塚
国重要文化財
東北歴史博物館蔵 |
遮光器土偶
(縄文晩期)
岩手県岩手町
豊岡遺跡
岩手県立博物館蔵 |
笑う岩偶
(縄文晩期)
秋田県北秋田市
白坂遺跡
県指定文化財
北秋田市教育委員会蔵 |
|
| 第2章 古代の薬師・観音信仰 |
|
|
|
|

| 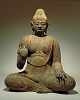
| 
| |
|
|
線刻千手観音等鏡像
秋田県大仙市
水神社
国宝
|
木造薬師如来坐像
宮城県栗原市
双林寺
国重要文化財 |
銅造観音菩薩立像
青森県おいらせ町
聖福寺
青森県重宝 |
|
|
|
| 第3章 武家と信仰 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
泥足毘沙門天立像
(上杉謙信守本尊)
山形県米沢市
法音寺蔵
※展示期間…
10/14(水)~11/1(日)
|
白糸威肩赤胴丸
(兜・大袖付)
青森県八戸市
櫛引八幡宮蔵
国重要文化財 |
太刀 銘 来国光
宮城県塩竈市
鹽竈神社蔵
国重要文化財 |
金梨地菊竹に雀紋蒔絵
糸巻太刀拵
宮城県塩竈市
鹽竈神社蔵
国重要文化財 |
|
|